
最近勉強会登壇記事関係ばかりが連続していますが、表題の通り、CivicTechLTというイベントに登壇してきました。
今回はシビックテックをテーマとしたイベントということで、自分含み4人の人が参加。それぞれのシビックテック活動事例についてお話をしました。持ち時間は一人15分程度 ということでわりとゆっくりめ。
わたしも最近LTイベントの感覚を忘れつつあったのでちょうど良かったかな。
自分の内容
今回発表した内容は、ポッドキャストについて。
自分が配信しているSBCast.やstand.fmでやってるちえラジChatの話しからはじまり、今なぜポッドキャストなのか、ポッドキャストをやるとしたらどういう風にすれば良いのか という話をしました。
ポッドキャストならではの魅力
ポッドキャストには、個人的にはいくつかポッドキャストにしかない魅力があると思っています。
そこまで興味はないけどちょっと興味があることをなんとなく知る
まずは、そこまで興味はないけどちょっと興味あることを知る手段として。
文章や動画は、それを確認するのにそれなりの時間がかかります。
文章を読みながら全く違う文章を書いたり、全く関係ない動画を見ながら料理をしたり なんてことはできません。
だからこそ、その分野にすごく興味があるということであればともかく、(多少興味はあるけど)時間を割くほど興味を持ってるわけじゃないみたいな分野の文章や動画は、読まれないし見られない。
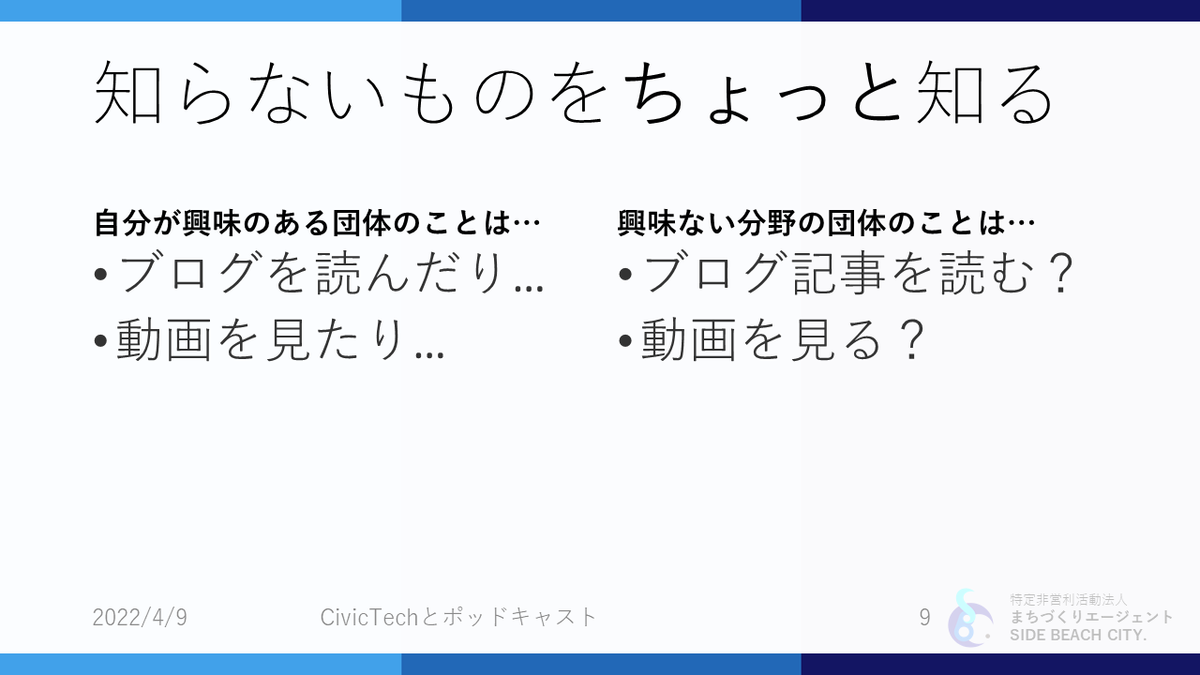
でも、ポッドキャストであれば、それが出来る可能性がある。
料理中でも、入浴中でも、コーヒーを煎れに離席しているちょっとした合間でも、いろんな時間にながら聞きができる。
そのため、そこまで興味はないけど、ちょっと興味はあるかなというような内容にも、触れる可能性が生まれてくる。
今まで隙間時間になり得なかった時間を隙間時間にする。
そして、上でも書いたとおり、ポッドキャストは動画や文章を読めない間にも、情報を流し込むことができます。
最近は8分とか、15分とか、割と短めのポッドキャストも多い。
なので1.5倍速くらいで再生すれば、それこそトイレに行って帰ってくるまでの間で1エピソード聞き終わる なんてことも不可能じゃない。
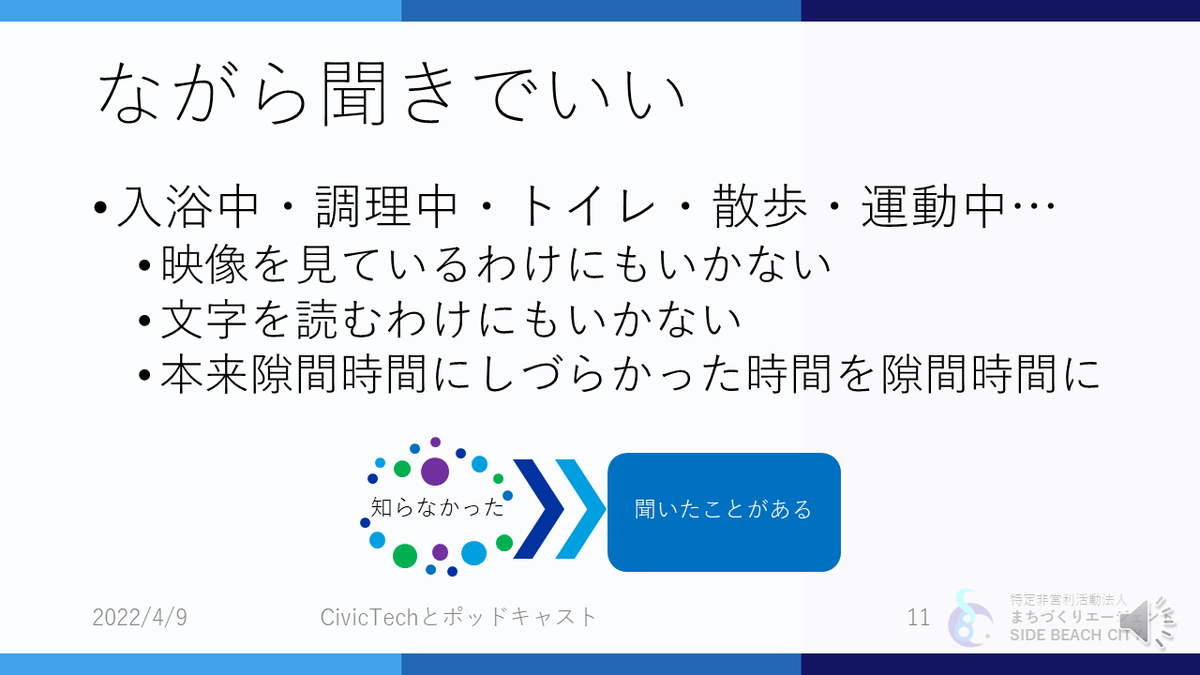
だからこそ、今まで隙間時間になり得なかった時間を、あますことなく情報収集の時間に変えることができます。
情報のシャワー
ポッドキャストは情報のシャワーのような意味があるんじゃないかな と考えています。
8割くらいの情報は受け取ることができないけど、2割くらいの情報はしっかりと残る。
「知らなかった」ことを、「聞いたことがある」に変えることができる。それは結構大きいのかなと思っています。
シビックテックとポッドキャスト
シビックテックって範囲がやたらと広く、高齢者支援の活動をシステム化するとかでも、子育て支援団体のZoom利用を手ほどきするとかでも、地域活性化のためのサイトを作るでも、なんでもシビックテックになり得てしまう。
なので、全容は知らなくてもいいけどなんとなくしっている分野が広くないといけなかったりします。
そういう分野の情報を仕入れるために、ポッドキャストがいいと思っています。
なにより長く続いているシビックテック系ポッドキャストは多くない
なにより、(自分はGoogle Podcastsでポッドキャストを聞いているため、Spotifyオリジナルなどは見ていないのですが、)シビックテックや地域課題に関するポッドキャストで、かつ今も定期的に続いているものは、それほど多くない。
とくに地域関係の団体は、途中で更新をやめてしまったものが多く、個人的にはとても寂しく思っています。
だからこそ、今回のイベントに興味があるような人に、もっとポッドキャストをやってほしいな と思って、今回のような発表となりました。
そのほかの発表に思うこと
そのほか、LTではエンジニアの方々による活動報告のほか、まちづくりエージェント SIDE BEACH CITY.の万代裕美さんにもお越し頂いて、活動の紹介がありました。
万代裕美さんの活動は正直そこまでしっかり見られているわけではなかったので、活動の解像度が上がった気分です。
しかし、エンジニアが多かったなあということと、課題ドリブンではなく、スキルを試す場としてシビックテックというものを選んだ人って、多いんだろうなあ ということを思いました。
告知場所がconnpassだったので当然といえば当然なのですが、エンジニアではない人の声は、あまり聞くことができなかった。
シビックテックに関わる、けどエンジニアではない人は、どういう想いを持ってこのような活動をしているのだろう?というのが、非常に気になります。
とくにSBCast.で聞いた限りでは、Code for Japanブリゲイドにも、非エンジニアの方、地域行政に関わる方が数多くいると聞きます。
そういう人たちの声や課題を、もっと聞いてみたいな と思いました。