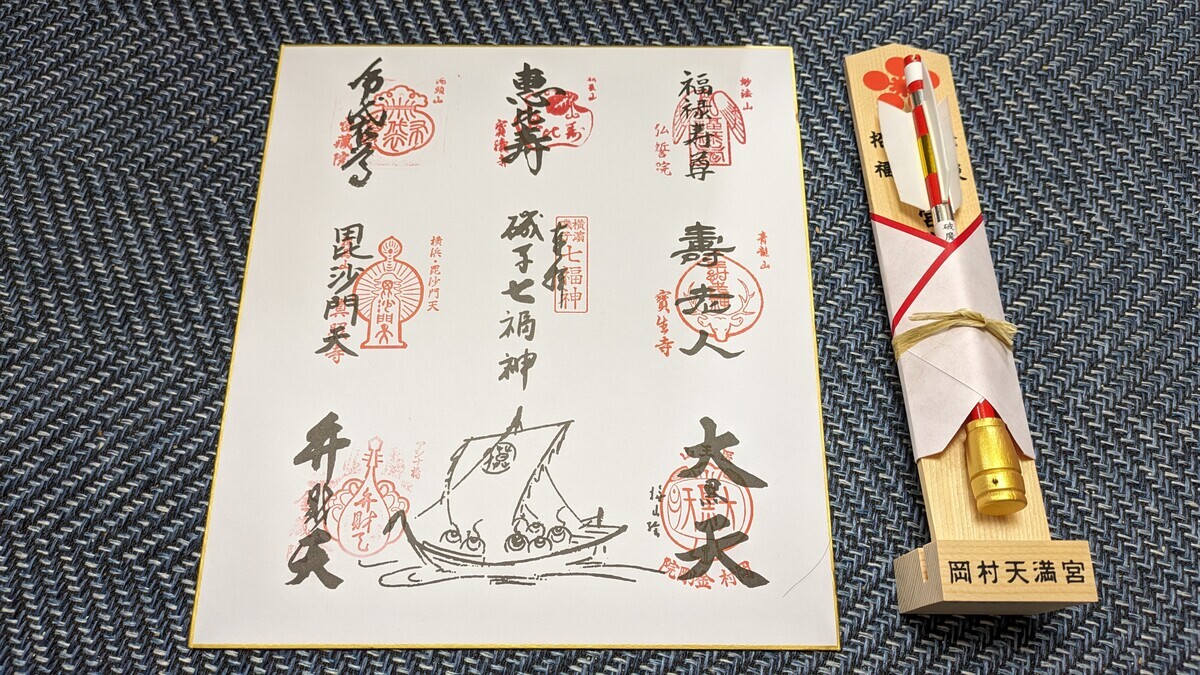さすがに何も書かずに過ごすのもどうかと思ったのでこちらにも。
表題のとおりではありますが、6月27日で41歳になりました。
早いもので前回その辺のブログを書いてから一年経ってしまったということになります。早いものです、意外と何もできていません・・・。
今年の6月27日は木曜日、山手縁乃庭での活動がありましたので、ゲームの誕生日イベントにはほとんど立ち合えませんでした。
とりあえずあつまれどうぶつの森では一日過ぎちゃったけどのメッセージを受け取ることができましたが・・・。
いままでやってきたこと
昨年と同じようにTogglを使って今年一年を振り返ってみると、やはり音声発信が非常に多い一年でした。
ポッドキャストのSBCast.にビデオポッドキャスト的な側面もあるSBC.オープンマイク、そして今年から始まったSIDE BEACH CITY.の活動をもっと深掘りするSBCast. Ch2、そして個人での配信であるちえラジChat。
またここ最近ほかのポッドキャストの立ち上げにも関わっているため、音声配信に関わる機会はどんどん増えています。
音声で発信を続けることで、普段は文字にしないようなことも意外と簡単に表現できる。
SBCast.やSBC.オープンマイクで他の団体の方々の話を聞いていても、公式記事には書かないけれど大切にしていることや、公式には書かれない設立の背景など、話を聞くことで改めてその人の活動をもっと立体的に知ることができる。
これらを記録として残せるというのも音声による情報発信の大きな価値なのだなと、最近感じています。
LISTENという存在
さらに今であればLISTENもあります。
LISTENを使うことで音声だけでなく文章としてその内容を読むこともできる。
音声で聞きたい人は音声として、文章で読みたい人は文章として、好きな方法で情報を知ることができるようになった。
その分「でも音声は聞くのにコストがかかるからなぁ」とかそういうことを気にしなくてよくなったというのも大きいかなと最近思っています。
自分の活動をなかなか表に書いていられない、そういうような人たちにはポッドキャストを積極的に勧めてみたい。
最近特にそういうようなことを感じるようになりました。
AIによる文字起こしと、読ませるために書いた記事
もちろんそれでもAIによる文字起こしされた音声ともとよりテキストとして読ませるために書いた記事は全く違うし、いくら「えー」とか「あの」とかのフィラーを削除したとしても、断然元からテキストとして読ませるために書いた記事の方が読みやすい。
時間に余裕があるのであれば音声として喋った事をテキストとしてリライトするということもやっていきたい。
去年はやると言っておきながら全然できなかったので、これは来年度から頑張っていかなければいけないなと思うところではあります。
これからやって行きたいこと
来年度からは実はSIDE BEACH CITY.のプログラミング授業の活動が徐々に増えており、学校だけでなく、いろんなところで講師をやることになっています。 個人でもそういうような事業は作っていきたいなと思っています――といいつつまだ何もできてないんですが――
今のプログラミングって初心者向けと上級者向けの内容はそこそこあるものの、中級者向けの情報って案外足りない。
そして初心者向けと言ってももうその時点でそこそこのレベルがあり、本当に初心者向けの情報って意外とない。
だから、プログラミングにもっと気軽に触れられる情報源や、さらにスキルを高められる情報源はどんどん増やして行きたいなと思います。
ギークがもっと居られる地域を
また今までの話の中でもちょくちょく取り上げてきましたが、パソコンやインターネットなどの知識があり、それらの活動を楽しむ、いわゆるギークがもっと居やすい地域を作っていきたい。
自分がいろんな場所に顔を出すことで存在感をアピールして行くことももちろん、そういうような人の活動にフォーカスするようなことも増やして行きたいなと思っています。
もちろんできることに限りはあるのでほどほどに時間を使いながら関わっていきたいと思うのですが。
ただSBCast.の活動ですとか、その他のSIDE BEACH CITY.の活動ですとかで、少しでもそういうような人たちの存在感が多くの人に伝わるようなことができればなと。
AIに関して
それからここ最近のことといえばAIなんかもありますね。 自分は常々言っている通り、ほぼ毎日1個、Bing Image Creatorに画像を作ってもらうという試みをしています。
その他最近はSunoによる音楽生成や、Perplexityなどの文章生成AIを使った地域情報の調査などもはじめました。
ただ地域で話をしていると、そういうようなものを使っている人と使っていない人は極端に分かれてしまう。ちょうどよく使って何かを考える ということをしている人が意外といない。
地域の人がそういうAIだとかさまざまなツールを使えば何ができるのだろうかというのは個人的には非常に気になるところです。
だからこそもっとこれらのツールを使ってみるという人が地域に増えてくれば自分ももっと新しいものを見られるのかなと思っています。
どこまでできるのかどういう形でできるのかわかりませんが、もっと地域の人が面白いものに気軽に触れられる環境というものを作っていきたいなと。
今後に向けて
結局また流されるように41歳になってしまった今の自分。
ただ今年こそ、ある程度のことはできたなと、自信を持って言えるようにしたいなと思います。
そのためにはSIDE BEACH CITY.の中のことも、SIDE BEACH CITY.以外のことも、しっかりと顔出していかなくちゃなと。